普段何気なく食べているチョコレート。
実は、味噌やワインと同じ「発酵食品」だということをご存知でしょうか?
チョコレートの風味の大半を決めるのが、カカオ豆の発酵工程です!この工程がなければ、チョコレート特有の芳醇な香りも、まろやかな味わいも生まれません...
本記事では、チョコレートに欠かせない発酵カカオの仕組みと、発酵がもたらす味わいの変化について詳しく解説します♪発酵の知識を知れば、いつものチョコレートがもっと美味しく感じられるはずです。







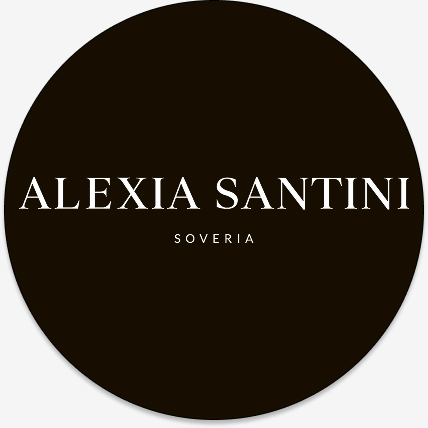

































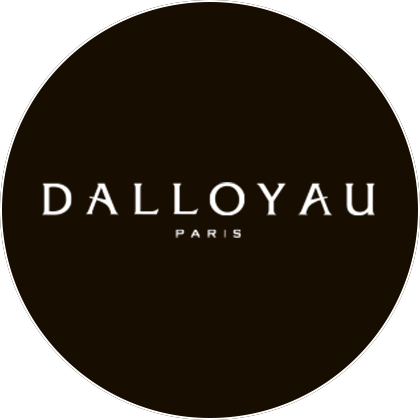






















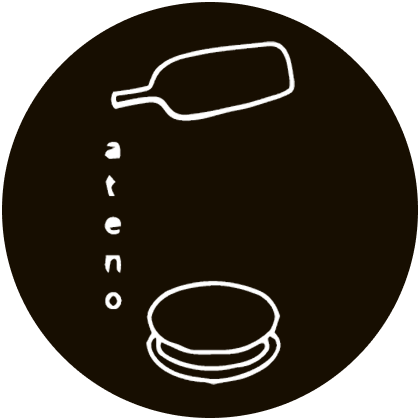




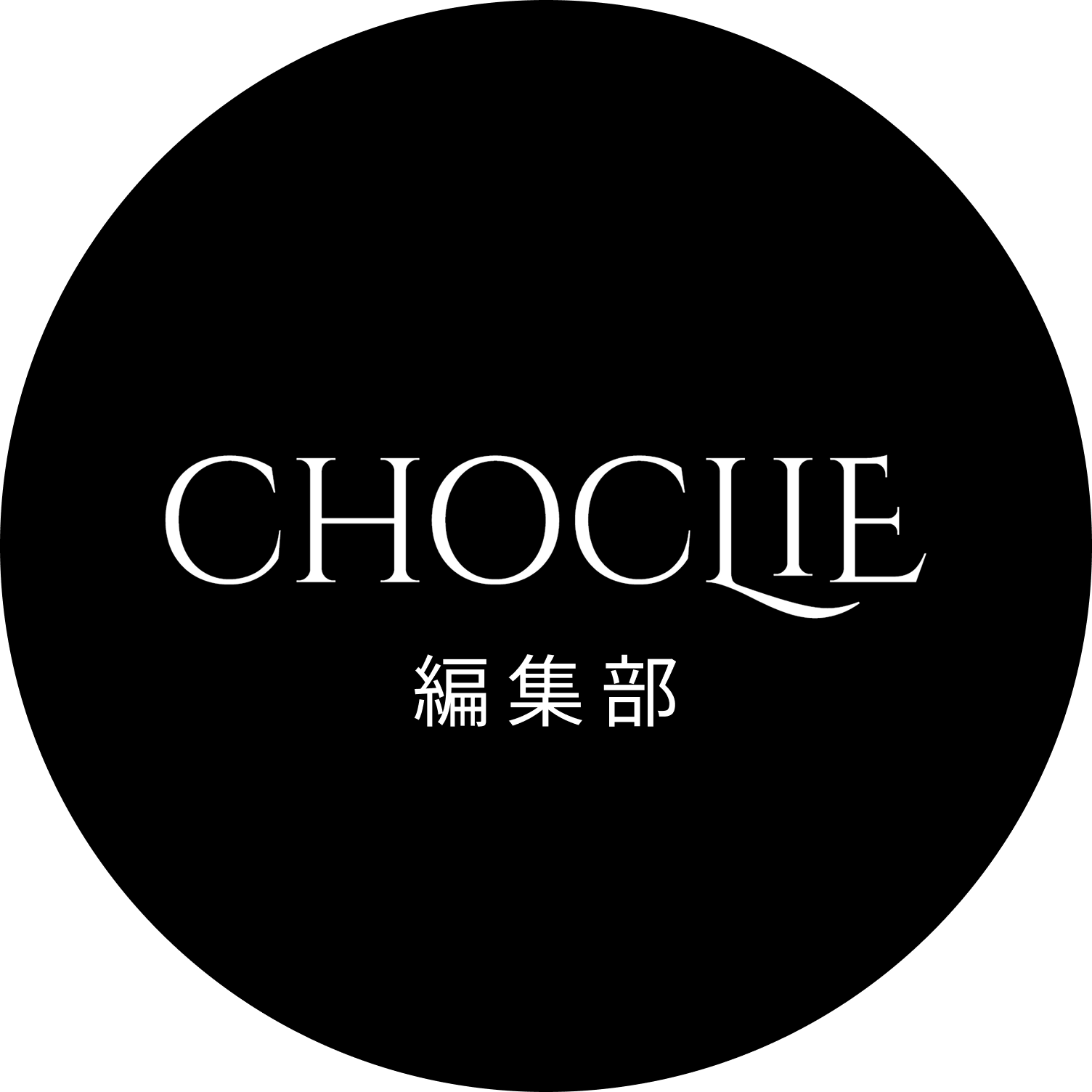

普段何気なく食べているチョコレート。
実は、味噌やワインと同じ「発酵食品」だということをご存知でしょうか?
チョコレートの風味の大半を決めるのが、カカオ豆の発酵工程です!この工程がなければ、チョコレート特有の芳醇な香りも、まろやかな味わいも生まれません...
本記事では、チョコレートに欠かせない発酵カカオの仕組みと、発酵がもたらす味わいの変化について詳しく解説します♪発酵の知識を知れば、いつものチョコレートがもっと美味しく感じられるはずです。

発酵カカオとは、収穫したカカオ豆を微生物の力で変化させる工程を経たものを指します。
カカオポッドと呼ばれる実から取り出したばかりの豆は、白いヌルヌルとした果肉(カカオパルプ)に包まれています。
この状態で木箱やバナナの葉に包み、数日間置いておくことで自然発酵が始まるのです。
☑ チョコレートは味噌やヨーグルトと同じ「発酵食品」
☑ 発酵によってカカオ豆の成分が大きく変化する
☑ 一般的なチョコレート製品では、発酵工程は生産国で行われる
発酵には酵母、乳酸菌、酢酸菌などの微生物が関わり、チョコレートの香りや味の基礎となる成分を生成します。
発酵していないカカオ豆をそのまま食べると、淡白で渋く、生臭いアーモンドのような味がします...これはカカオ豆に含まれるタンパク質やポリフェノールが、そのままの状態では美味しくないためです。
発酵していない豆は紫色をしており、チョコレートらしい香りもほとんどありません。
また発酵しないと豆が発芽しようとして、チョコレート作りに必要な脂肪分やアミノ酸を消費してしまうんです。

発酵によって生まれる最も重要な変化が、香り成分の生成です!
発酵期間中、カカオ豆の中では「プレアロマ」と呼ばれる香りの前駆体が作られます。
これが後の焙煎工程で熱を加えられることで、チョコレート特有の芳醇な香りへと変化するのです♪
発酵で生じる化学物質は数百種類に及び、チョコレートの複雑な風味を作り出します。
カカオ豆には強いポリフェノールが含まれており、そのままでは渋みが強すぎます。
発酵中に生じる酢酸や熱によって、このポリフェノールが酸化して変化。
その結果、渋みや苦味がマイルドになり、食べやすい味わいになるのです。
同時にタンパク質が分解されてアミノ酸が生成され、旨味成分も増えていきます。
発酵前のカカオ豆を割ると、中身は鮮やかな紫色をしています。
これはポリフェノールの一種であるアントシアニンによるもの。
発酵が進むにつれて、豆は徐々に茶褐色へと変化します。
この色の変化は発酵の進行度を判断する重要な指標となり、生産現場では豆を割って断面をチェックする「カットテスト」が行われています。

カカオの発酵は約5〜7日間かけて、3つの段階を経て進んでいきます。
発酵の最初は、酸素のない環境で行われる「嫌気性発酵」が起こります。
カカオパルプに付着している酵母が、果肉に含まれる糖分を分解してアルコールを生成。
この過程で熱が発生し、カカオ豆の温度は徐々に上昇していくのです。
またパルプの粘り気のある成分が分解され、液体となって流れ出ていきます。
2〜3日後、生産者がカカオ豆を攪拌することで空気が入り、「好気性発酵」の段階に移ります。
酸素を必要とする乳酸菌と酢酸菌が活動を始め、アルコールを栄養源にして酢酸を生成します!この段階で多くのエネルギーが放出されるため、豆の温度は40℃以上に達することもあるんです。
生成された酢酸が豆の内部に浸透し、重要な化学反応を促します。
発酵の終盤では、アルコールや酢酸、そして発酵熱によって豆の細胞組織が破壊されます。
この過程でタンパク質が分解されてペプチドやアミノ酸に、多糖類が単糖類へと変化。
ここで生じた糖とアミノ酸が、後の焙煎時にメイラード反応を起こし、チョコレートの香りを生み出します♪
発酵完了までには通常5〜7日程度かかり、この間にカカオパルプの大半は溶けてなくなります。
カカオ豆を包む白い果肉、カカオパルプは発酵に不可欠な存在です。
パルプには水分と糖分が豊富に含まれており、微生物が活動するための理想的な培地となります。
発酵はパルプで起こり、その成分が豆の内部に染み込むことで、カカオ豆そのものが変化していくのです。
パルプ自体もライチやパイナップルのようなフルーティな味わいがあり、産地では飲み物やジャムとして利用されています。

ヒープ法は、カカオ豆を地面に積み上げ、バナナの葉やシートで覆う伝統的な方法です。
西アフリカなどでは、手に入りやすいバナナの葉を使うこの方法が主流となっています。
シンプルな方法ながら、葉に付着している天然の微生物が発酵を促すんです。
ただし温度管理がしにくく、天候の影響を受けやすいという課題もあります。
ボックス法は、専用の木箱にカカオ豆を入れて発酵させる方法です。
中南米のプランテーションでは、階段状の木箱を使い、上から順に下へ移動させながら発酵を進める方式が多く採用されています。
箱の底には隙間があり、発酵で溶けたパルプの液体が流れ出る構造になっているのです。
ヒープ法と比べて衛生的で、品質を安定させやすいメリットがあります。
発酵の品質を決めるのが、温度管理と攪拌のタイミングです。
発酵が進むと豆の温度が上昇しますが、高温になりすぎると微生物が死滅してしまいます。
そのため2〜3日ごとに豆を攪拌し、酸素を取り込みながら温度を調整する必要があるのです。
この作業の頻度や方法は地域や生産者によって異なり、それがチョコレートの個性につながります。

発酵期間を短めに設定したライト発酵のカカオは、シャープで尖った味わいを持ちます。
酸味を好む方や、カカオの個性をダイレクトに味わいたい方に向いています♪
長めの発酵期間を経たディープ発酵のカカオは、まろやかで繊細なフレーバーを生み出します。
より洗練された風味を求める方に好まれる傾向があります。
発酵の管理によって、チョコレートの酸味の種類も変わってきます。
適切に発酵されたカカオは、爽やかな柑橘系やベリー系の酸味を持ちます。
一方で発酵が不十分だと渋みが残り、過発酵では酢のような不快な酸味が出てしまうのです。
発酵のコントロールは、チョコレートのフレーバーノートを決定づける重要な要素といえるでしょう。

中南米では、木箱を使った管理された発酵方法が一般的です。
エクアドルやベネズエラなどの産地では、プランテーション規模での生産が行われており、発酵設備も整っています。
そのため品質の安定した発酵カカオが生産され、フローラルで芳醇な香りを持つカカオが多いのです。
中南米産のカカオは、風味の複雑さと華やかさで評価されています♪
世界のカカオ生産量の約7割を占める西アフリカでは、小規模農家による生産が中心です。
ガーナやコートジボワールでは、バナナの葉を使ったヒープ法が主流となっています。
比較的シンプルな発酵方法ですが、力強いカカオらしい風味を持つ豆が生産されるのです。
西アフリカ産のカカオは、安定した品質とクラシックな味わいで、チョコレート業界を支えています。
インドネシアなどの東南アジアでは、伝統的に発酵管理が十分でない地域もありました。
発酵していない豆が混ざることで品質にばらつきが生じ、渋みの強いカカオになりやすかったのです。
しかし近年では、日本の発酵技術を取り入れた温度管理や、独自のスターターを使った発酵改善が進んでいます!
東南アジアのカカオは、発酵技術の進化とともに新たな可能性を見せ始めています。

カカオに豊富に含まれるポリフェノールは、発酵によってその形が変化します。
発酵前は渋みが強すぎて食べにくかったポリフェノールが、発酵と酸化によってマイルドな形に変わるのです。
とはいえカカオのポリフェノール自体は発酵後も豊富に残っており、抗酸化作用などの健康効果は保たれています。
発酵は、ポリフェノールの健康効果を保ちながら食べやすくする工程ともいえるでしょう。
発酵によってカカオ豆のタンパク質が分解され、アミノ酸が増加します。
このアミノ酸は旨味成分として働き、チョコレートの味わいに深みを与えるのです!昆布や鰹節に含まれるアミノ酸と同様の成分が、カカオ豆にも生成されるというのは興味深い点といえます。
発酵食品が腸内環境に良い影響を与えることは広く知られています。
発酵カカオも同様に、発酵過程で生成される成分が腸内細菌のバランスをサポートする可能性があるのです。
特にカカオに含まれる食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなります。
ただしチョコレート製品には糖分も多く含まれるため、食べ過ぎには注意が必要です。

チョコレートのパッケージには、発酵に関する情報が記載されていることがあります。
これらの表記がある製品は、生産工程にこだわっている証拠です♪パッケージの情報をチェックすることで、発酵にこだわったチョコレートを見つけられます。
Bean to Barと呼ばれるスタイルのチョコレートは、カカオ豆から一貫して製造を行います。
このスタイルでは、生産者と直接契約して発酵からこだわったカカオ豆を仕入れることが多いのです。
中には自ら産地に赴いて発酵指導を行い、理想的な風味を追求する作り手もいます。
Bean to Barのチョコレートは、発酵の違いによる味わいの個性を楽しめる製品が多いといえるでしょう。
チョコレートのフレーバーノートから、ある程度発酵の特徴を推測できます。
☑ 「フルーティ」「ベリー系」「爽やかな酸味」→ ライトな発酵の可能性
☑ 「ナッツ」「キャラメル」「まろやか」→ しっかり発酵が進んだカカオ
風味の説明を読むことで、自分の好みに合った発酵度合いのチョコレートを選べます。

カカオニブは、焙煎したカカオ豆を砕いたもので、発酵カカオの風味をダイレクトに味わえます。
カリッとした食感とカカオ本来の味わいが特徴で、砂糖などは一切加えられていません。
そのままナッツ感覚で食べたり、ヨーグルトやスムージーにトッピングしたりと、様々な楽しみ方ができます♪
毎日少量ずつ食べることで、カカオポリフェノールを手軽に摂取できるのも魅力です。
低温でじっくり発酵させたローカカオは、酵素や栄養素を壊さないよう加工されています。
通常の焙煎よりも低い温度で長時間処理することで、カカオの風味と栄養をより多く残せるのです。
健康志向の高い方に人気があり、カカオ本来の個性を楽しめる製品として注目されています。
ただし通常のチョコレートとは異なる風味なので、最初は少量から試してみるとよいでしょう。
発酵カカオは、チョコレート以外にも様々な形で日常に取り入れられます。
発酵カカオの風味を知ることで、チョコレートだけでない楽しみ方が広がるでしょう。

カカオの発酵は、チョコレートの風味を決定づける最も重要な工程です。
微生物の働きによって香り成分が生まれ、渋みが取れ、複雑な味わいが形作られます。
発酵の方法や期間、産地による違いを知ることで、チョコレートを選ぶ楽しみも広がるでしょう♪
次にチョコレートを手に取る時は、その奥にある発酵のプロセスを思い浮かべてみてください。
きっといつもの一口が、より深く、より豊かに感じられるはずです...!
人気第1位!RippleSweetsのボンボンショコラ
人気第2位!ラメゾンショコラのハートギフトボックス
人気第3位!期間限定のチェリーボンボンショコラ
人気第4位!思わずパケ買いしたくなる生チョコレート
人気第5位!キャラメルボックス